【保育園の洗礼】少しでも親子の負担を減らすために、親ができる事前対策!
もうすぐ新年度。
保育園の入園を控えて、準備されている方も多いはず。
この時期に、「保育園」「入園」・・・などで検索すると「保育園の洗礼」というなんとも恐ろしい言葉が出てきます。不安にしかならないです。
何を隠そう、我が家も「保育園の洗礼」に悩まされました。
この記事では、「保育園の洗礼」って?どう対策するのがいいの?という疑問や不安が少しでも解決できれば良いなと思って書きました。
我が家がどう対策したかも載せますので、参考になれば幸いです。
「保育園の洗礼」とは?
子どもが保育園に入園する際に、多くの親が経験する「保育園の洗礼」。
これは、子どもが風邪やウイルスなどの感染症にかかることを言います。体もまだ成長段階にあり、免疫もまだ確立されていません。抵抗力も十分にないため感染症にかかりやすい状態です。
新しい環境に適応するための正常な反応とも言えます。
また、保育園では集団生活を送るため、感染症をもらいやすい環境でもあります。
「保育園の洗礼」はどれくらい続く?
保育園の洗礼が続く期間には個人差がありますが、多くの場合、入園初期から約3ヶ月間がピークとされており、この間に多くの子どもが風邪や発熱などの症状を経験します。3ヶ月以降は、少しずつ体調が安定していく子どもが多く見られますが、年度替わりや季節の変わり目は注意が必要です。
保育園の洗礼は、主に入園当初の数ヶ月間に集中しますが、年齢によってその持続期間は異なります。0歳から2歳の幼児は、特に免疫力が未熟なため、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすく、この時期に多くの病気を経験することになります。3歳以降になると、徐々に免疫が強化されるため落ち着いていきます。
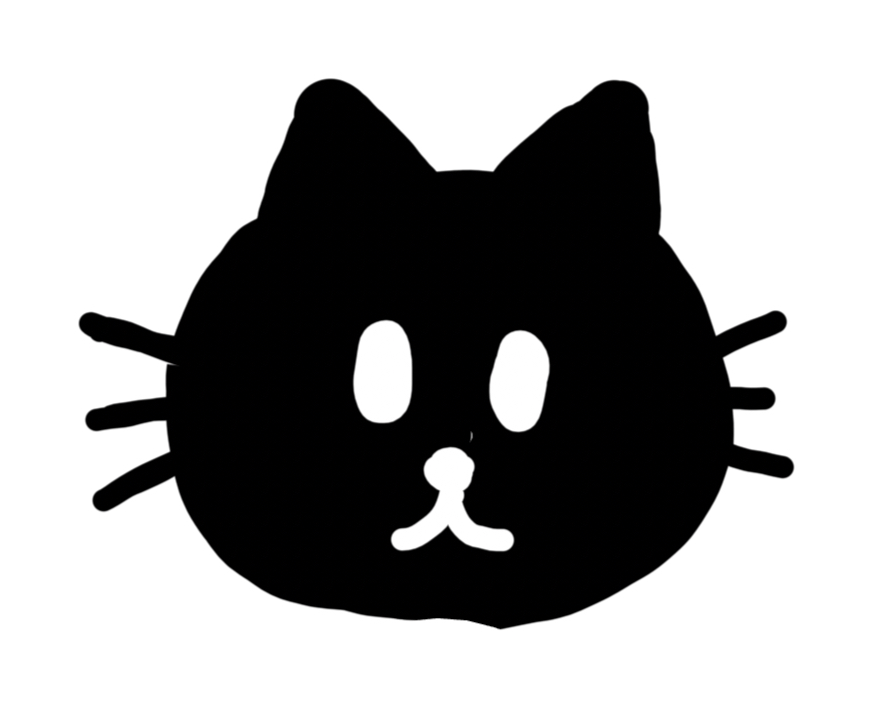
うちは0歳から預けたので、月の半分は風邪ひいて保育園をお休みしていました。1歳になったあたりから、ほぼお休みなく通えています!成長したし、身体も強くなりました!

1歳の誕生日が過ぎてから、1回ぐらいしか熱は出てません。しかも、次の日にはケロッとしてるよ。
「保育園の洗礼」子どもの症状は?
鼻水や咳、発熱、さらには嘔吐や下痢など、さまざまな症状が見られます。初めのうちは、親もその変化に戸惑うことが多いでしょう。例えば、風邪の引き始めには、鼻水や咳、うんちが緩くなるといった軽い症状から始まることが多くいため、見逃さないようにしましょう。
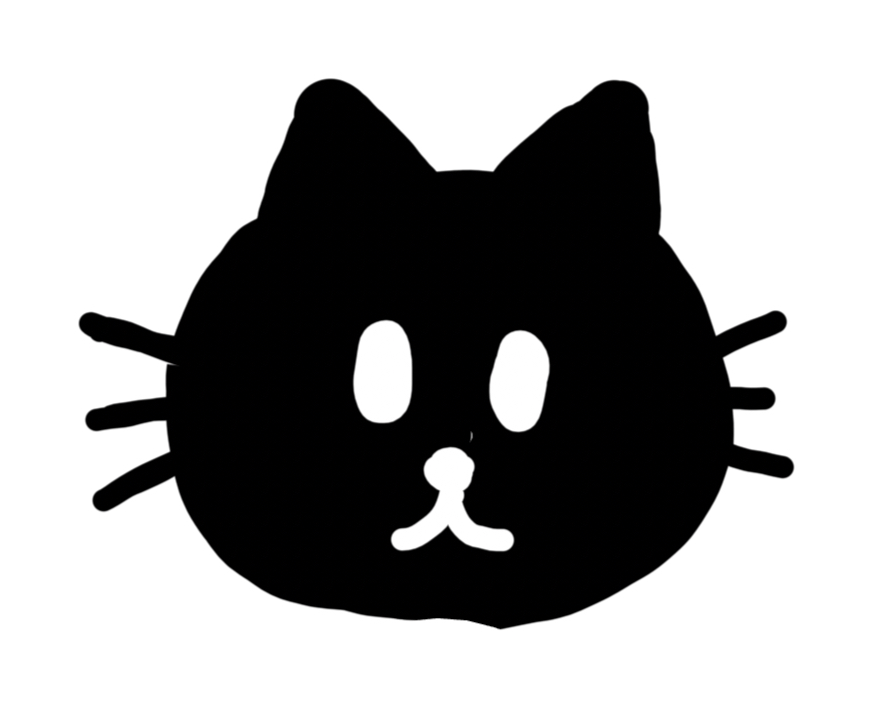
ことらくんの場合は、「よだれ」が急に多くなってくるのが体調不良のサインでした!鼻が詰まって、口呼吸になっていたのかしら???
「保育園の洗礼」親への影響は?
親も感染症にかかる
一番近くで看病しているのですから、子どもの感染症をもらう確立が高くなります。コンコンと咳をしている子どもを抱っこしたりと看病していたら・・・もらわない方が難しいです。
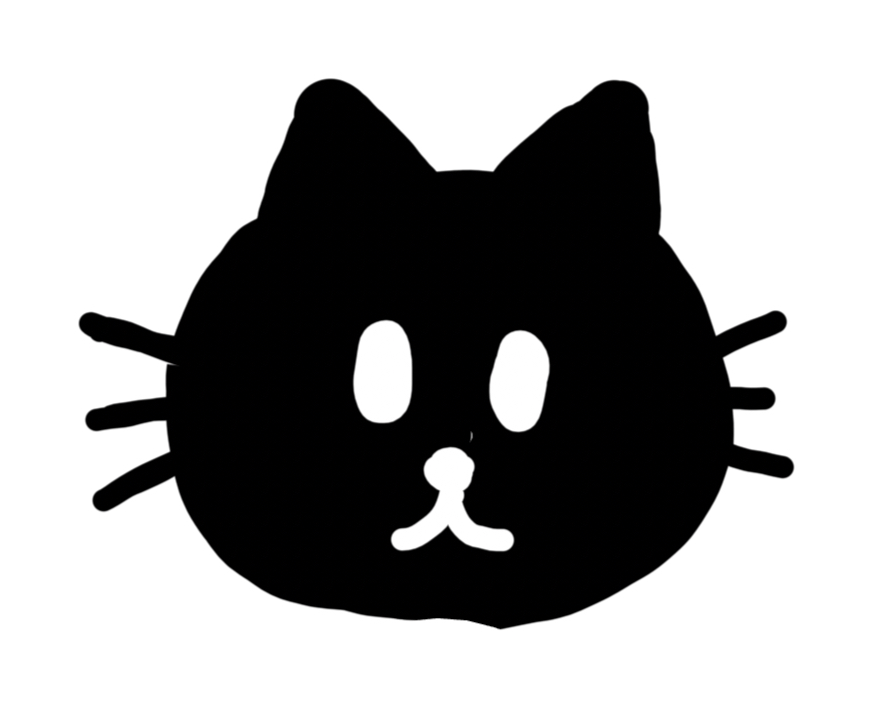
看護師なので、感染対策の知識は万全。仕事の中でいろんな感染症の人に関わっていたのに、もらうことはなかったので油断していました。こちらも、睡眠も十分に取れず免疫力???みたいな感じでヨレヨレでした。

ままにゃんにも風邪やインフルエンザを何回もうつしたよ!!自分も熱あるのに、看病してくれてありがと!
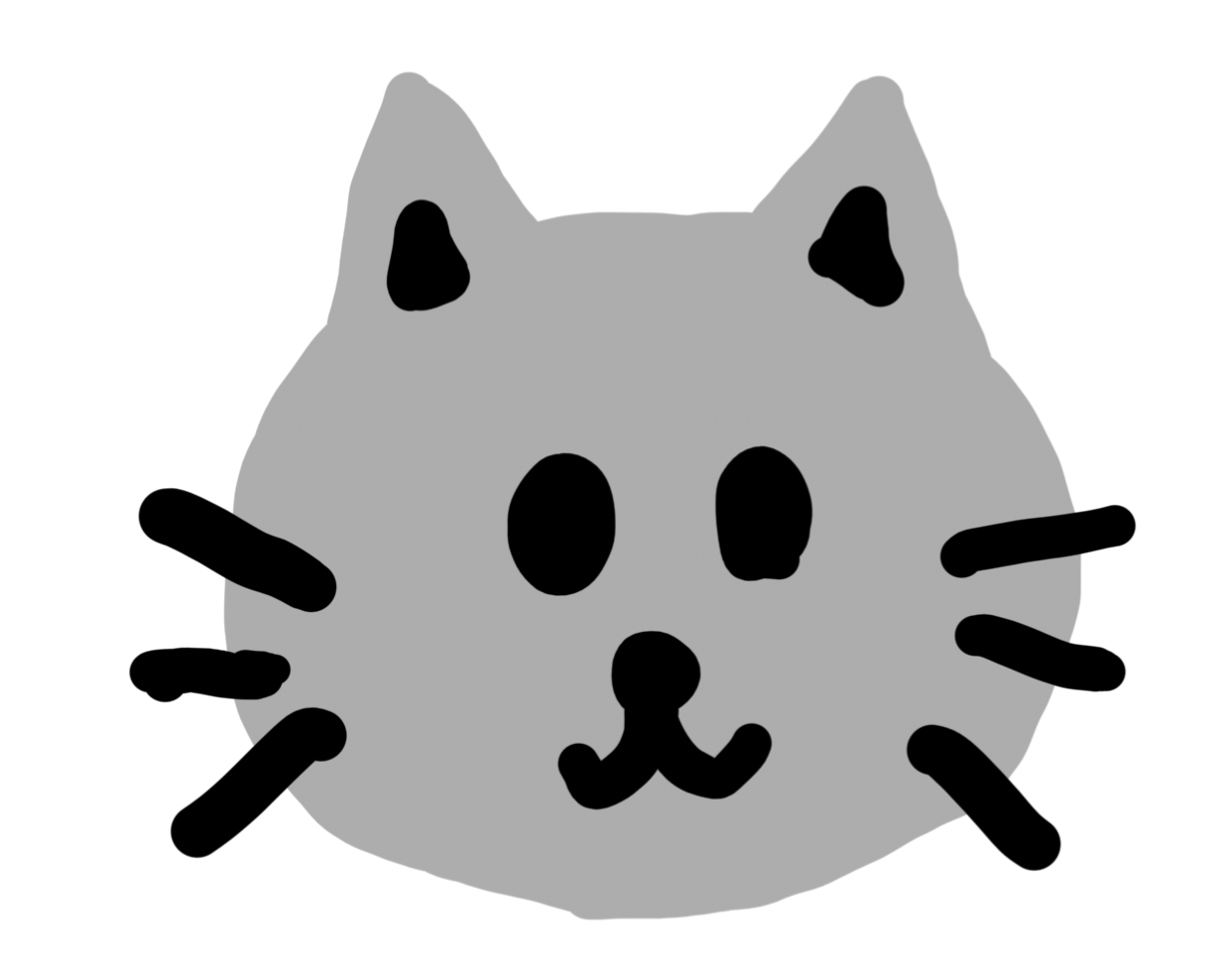
ことらくん→ままにゃん→ぱぱにゃんの順でみんなで風邪をひいて、家族全滅したことが何度かあります。だいたい、最初のことらくんはすぐに元気になって、ままにゃんとぱぱにゃんは風邪が治らず長引きます。若いって素晴らしい!です。回復力が違います!
職場によってはまさかの退職?
育休明けで、休みを取りにくいと思ってしまう時期です。保育園の洗礼に理解がない職場だと、「退職」という言葉が頭をよぎります。
職場のサポート体制を調べておいたり、家族のサポート体制の準備をしておく必要があります。
せっかく入園できた保育園。退職してしまうと、また就活からのスタートです。再就職したとしても親も新しい職場に適応していくのにいっぱいいっぱいになる可能性が高いです。
できるだけ退職せずに済むように事前の準備や対策が重要となります。
保育園の洗礼を防ぐ対策
「子ども」への対策ポイント5つ
手洗い・うがい
感染対策の基本の「手洗い」とうがいです。保育園から帰ってきて、まずお家でやることとして習慣づけをします。お気に入りのハンドソープなどがあると、楽しんで手洗いをやってくれます。

ピクミンのハンドソープがお気に入りで、手洗いが習慣になりました!
予防接種を受ける
予防接種は、特定の感染症の発症や重症化を抑える効果があります。小児科で予防接種のスケジュールを渡されることも多いので、しっかり予防接種をしておくと良いです。
乳幼児は、母からもらった免疫が下がる頃であるため、予防接種は重要です。
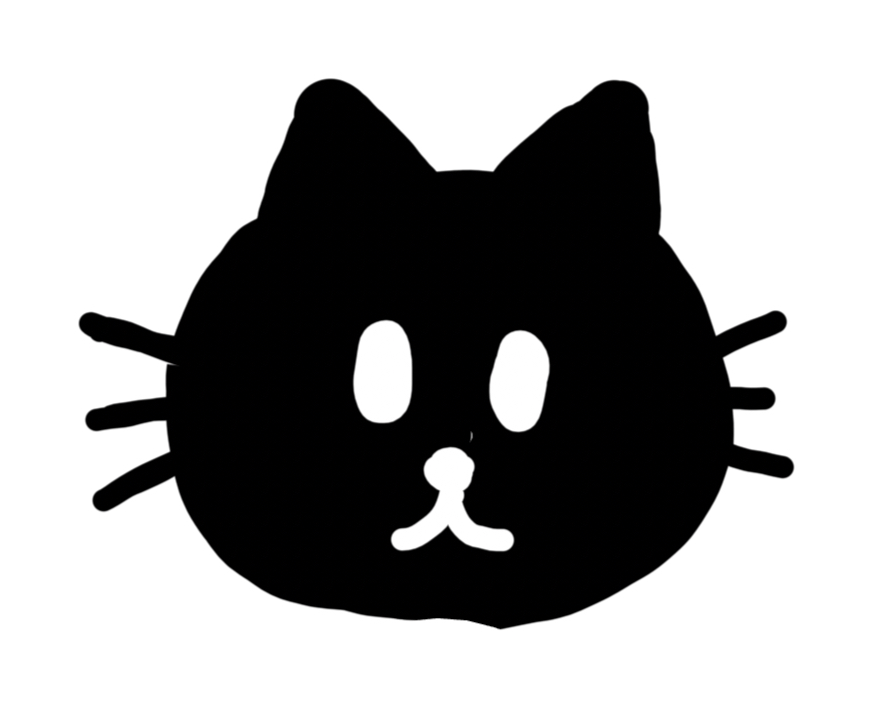
入園して最初の感染症は「ロタウイルス」でした。予防接種でロタをしていたので、重症化しなかったです。それでも、嘔吐と下痢はなかなか大変でした!

インフルエンザは1回目のワクチンを打つ日に罹ってしまい、げっそり痩せてしまいました。体の中のウイルス量が多くなると、ウイルス量を減らすために下痢で体の外に出そうとします。水分だけはしっかり取りました!
バランスの良い食事
腸内環境を悪化させてしまうと、免疫も下がりやすいです。発酵食品や食物繊維などを含む食品は腸内環境を整えてくれます。
とは言っても、好き嫌いなどもあってバランスの良い食事ができるとは限りません。取り合えす、お菓子とかではなくて、食事をしてくれてるだけで良しとしてもいいと思います。
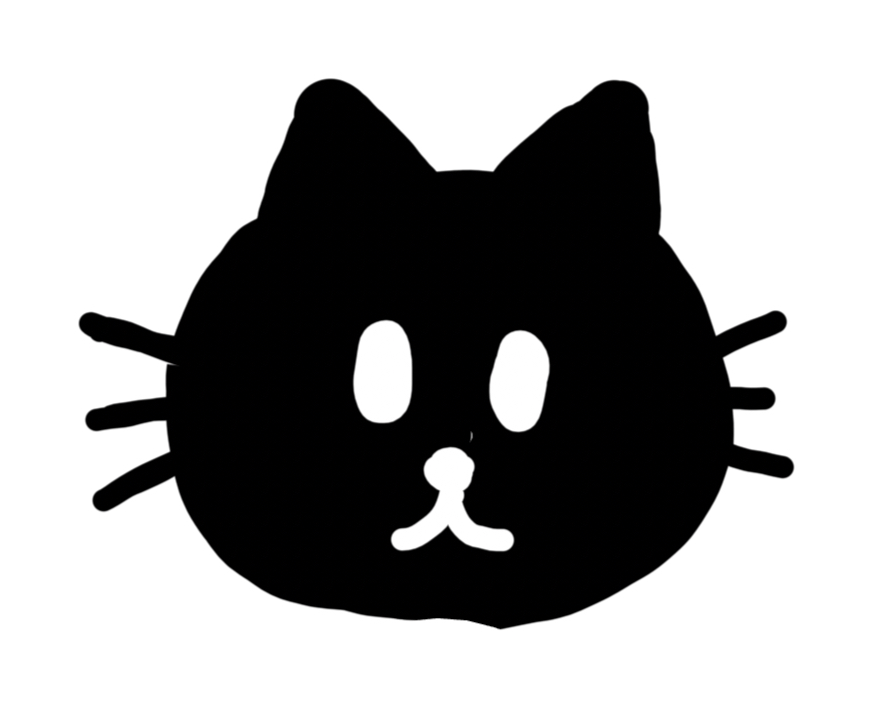
うちは困った時の「豚汁」です。野菜もお肉もお味噌の発酵食品も取れますしねー。しっかりお出汁で煮込んでるので、食べやすいみたいでニンジンも大根もモグモグ食べてくれます。しめじも好きです!
睡眠
早寝早起きが理想です。保育園に通う生活リズムに慣れるためにも、睡眠はしっかり取るのがおすすめです。睡眠は疲労回復させるだけでなく、免疫も上げてくれます。

僕は、20時〜21時に寝ると、次の朝は機嫌よく起きれます!
鼻水をこまめに取る
保育園い行くと、クラスの子みんなが「鼻水」!!!という場面をよく見ます。
鼻水が溜まって、そのままにしておくと、中耳炎になりやすくなったり「発熱」しやすくなります。乳幼児だと、まだ「鼻をかむ」という行為が難しいです。入浴後などに吸引器などで鼻水を取ってあげることをおすすめします。
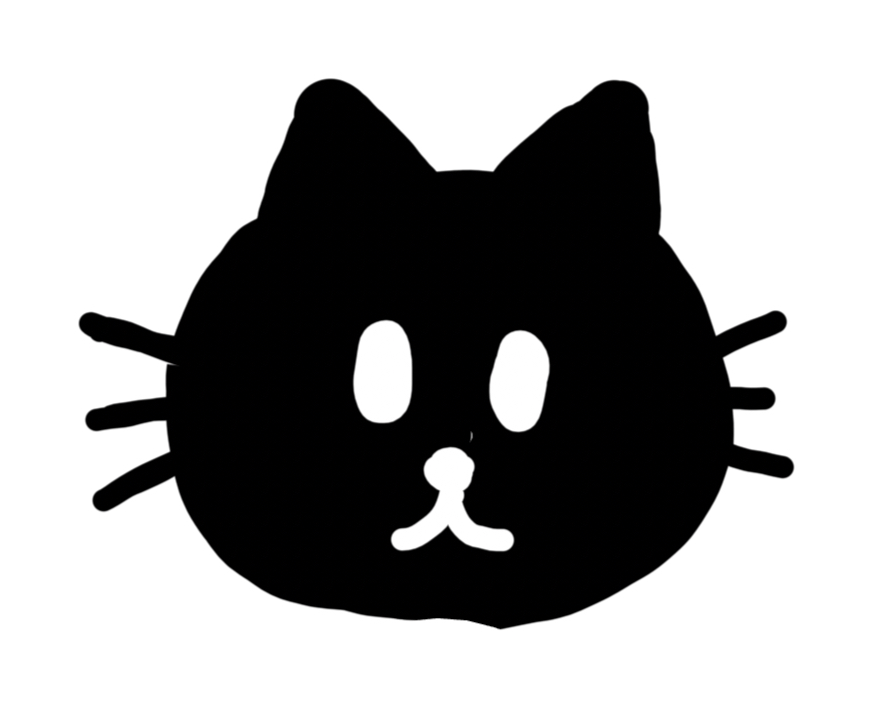
ことらくんの場合は、「よだれ」が急に多くなってくるのが体調不良のサインでした!鼻が詰まって、口呼吸になっていたのかしら???
子どもから「親」にうつさないためのポイント
手洗いうがいと鼻うがい
感染対策の基本の「手洗い」そして「うがい」。そして、意外とおすすめなのが「鼻うがい」。
帰宅時、食事前、オムツの交換後、嘔吐物の処理後・・・など。こまめな「手洗い・うがい」が有効です。
「鼻うがい」は、うがいよりも広い範囲で洗浄できるのでおすすめです。帰宅時や寝る前や朝起きた時にすると、風邪予防や花粉症の症状軽減にも役に立ちます。鼻が詰まって眠れない時などにもおすすめです。スッキリして、眠れます。
子どもの食べ残しを食べない
「もったいない」と食べてしまいがちですが、食べ残しを食べてしまうと、子どもの唾液の中にいるウイルスを取り込んでしまうことになります。
睡眠の確保
可能なら、子どもと一緒に早寝早起きをしましょう。親も体力勝負です。
子どもの変化に気が付けるように観察する
前触れもなく急に発熱や嘔吐することもありますが、何かしら予兆があれば親の心の準備も仕事のスケジュールの調整もつきやすいです。

体調悪くなる前に「よだれ」が急に多くなったりしたので、その子の前兆を見逃さないようにね!ロタはうんちが白っぽくなるよ!うんちの観察も役に立つよ!
急な発熱に焦らないために
子どもが発熱や風邪の症状を示した場合には、無理をさせずにしっかりと休むことが大切です。
風邪の場合、体を温め、十分な水分補給を行って安静にすることが推奨されます。また、症状が続く場合は、小児科の医師に相談し、適切な治療を受けることをお勧めします。
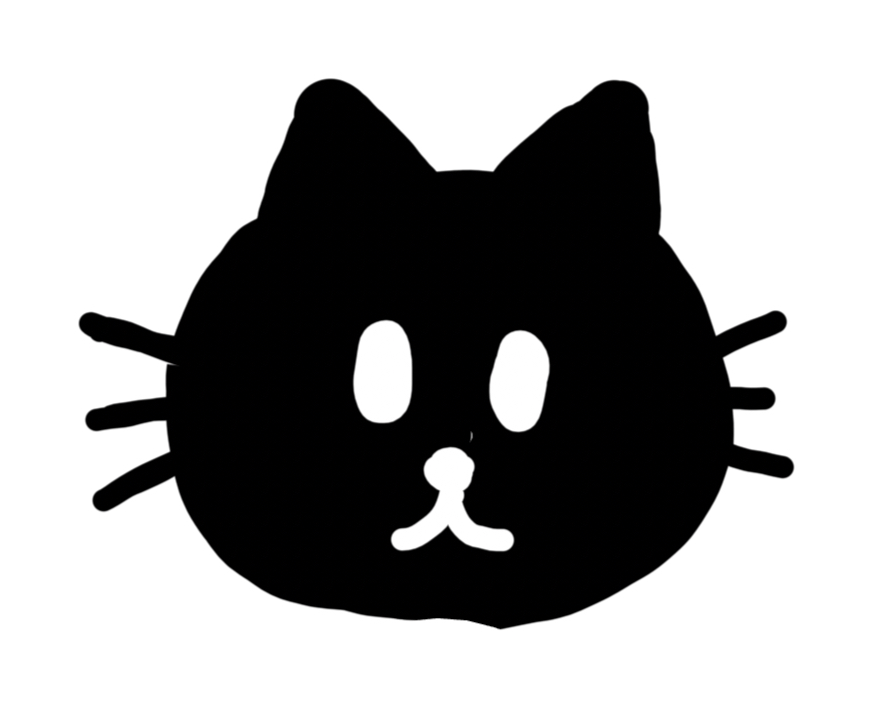
うちは早めに小児科に連れて行っていました。あと、薬は子どもの体重などによって量が変わるので、医師に多めに処方(整腸剤・解熱剤・風邪薬)してもらい、休日や夜中に焦らなくて良いように準備していました。おかげで、市販薬で子どもに合うものを探してドラックストアを回って・・・ということはありませんでした。

お薬の用法・容量はしっかり先生に確認して使ってね!
「保育園の洗礼」対策として事前に調べておくと助かること
保育園の感染症の種類別の休む基準
入園前のオリエンテーションなどで配布される「園のしおり」などに基準が掲載されています。基本的には感染症法などの法律を根拠に、感染症の種類や休む期間や基準が載っています。園によっては、登園許可証をかかりつけ医に書いてもらう必要があったりします。
かかりつけの小児科の営業時間や予約方法
最近はアプリで予約したりできる小児科も増えています。何時まで受付しているのかなど事前に把握していると、保育園の急遽のお迎え要請に対応できます。

僕の通っている保育園は、下痢が3回以上出たり、熱が37.5度以上の時はままにゃんがお迎えに来てくれて、そのまま小児科受診に行ったりするよ。
病児保育
まずは、お家の近くにどんな病児保育の施設があるかを調べておきましょう。事前の診察が必要だったり、保育園に預けるよりは、手順が多くなります。預けるまでに時間がかかるので、仕事の開始時間から逆算しつつ予約しないといけません。お弁当が必要な場合が多いようです。
最近は、自宅に看護師や保育士が来てくれる「シッター型の病児保育のサービス」をしている会社もあります。自分の住んでいる地域でも使えるのか調べてみても良いかもしれません。
地域のファミリーサポートの支援
地域によっては、有償ボランティアでファミリーサポートの支援があります。どういう時にお願いできるものなのか調べておくとよいです。
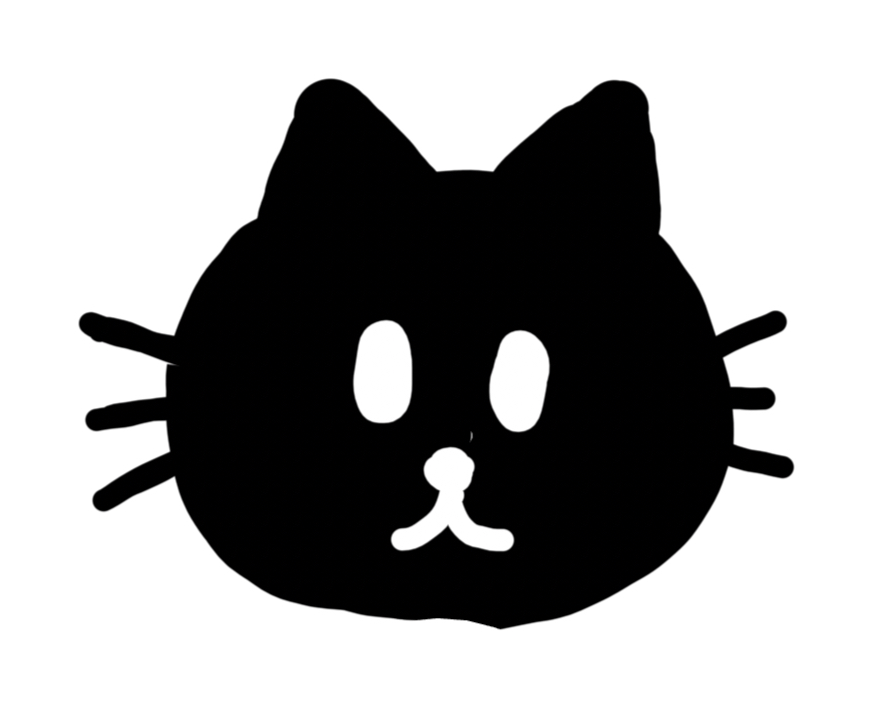
母子手帳を交付してもらった時に、地域の子育てお役立ち情報の冊子をもらいました。公的な支援がたくさん掲載されていました!もちろん、条件によっては使えない支援もありますので、要確認です!使えるものは積極的に使いましょう!
仕事を休む時の手順や親の有給残数
仕事を休む時は、仕事の調整が必要になります。できるだけ早く上司に相談しましょう。とは言っても、急遽休むことも多いはず。日頃から、子どもの体調など伝えておくのも良いかもしれません。
また、有給の残数の管理もしっかり行いましょう、家族の中で、誰が休むかなど相談や調整が必要です。
「育児・介護休業法」の改正内容と会社への確認
「育児・介護休業法」が2025年4月1日から段階的に改正されます。
「看護等休暇」の対象が拡大されて、病気・怪我・予防接種・健康診断に加えて「感染症に伴う学級閉鎖等」と「入園(入学式)、卒業式」でも休めるようになりました。しかも、対象となる子の範囲が拡大され、小学校3年生終了までとなりました。そして、「入社してすぐ」でも一応使えるようになりました。もちろん、男性も対象です。
注意点としては、看護休暇は有給か無給かは法律の定めはありません。ですから、会社に確認する必要はあります。
「保育園の洗礼」対策として購入して役に立ったもの

吸引器
吸引圧が一定で、家庭でも使える子供用の吸引器があります。

お鼻をかむことができないので、鼻水を取るために吸引器で吸引されたよ。最初は嫌だったけど、途中から自分でできるようになったよ。
加湿器
乾燥は大敵です。室内が湿度40%以上になるよう加湿が必要です。
空気が乾燥すると、喉や鼻の粘膜が乾燥して血流低下を引き起こし、免疫低下の原因となります。
喉や鼻に炎症をおこしやすくなるため、空気が乾燥する冬には風邪をひきやすくなります。
消毒液(ハイターやミルトン)
ハイターなどの次亜塩素酸ナトリウムは嘔吐の処理などで使用します。
哺乳瓶の消毒で使っていたミルトンも次亜塩素酸ナトリウムが主成分になるので使えます。
手に触れるものの拭き掃除用:500mlペットボトルに水を満杯にしてハイターを10ml入れる
つけおき用:水1リットルに対して、ハイター50mlを入れる
しっかり、手袋とマスクをして処理してください。
鼻うがいキット
サイナスリンスなど鼻うがいのセットがドラックストアなどで購入できます。生理食塩水を作って鼻の中を洗うので痛くないです。子どもは手技的に難しいかもしれませんが、子ども用のセットも売っています。

「保育園の洗礼」対策としてサポート体制を確保
祖父・祖母など、家族を総動員する
子どもが元気な時に、時々、祖父や祖母に保育園の送り迎えをしてもらっています。
どうしても親が都合がつかない時、急遽のお迎えを頼みやすくなります。
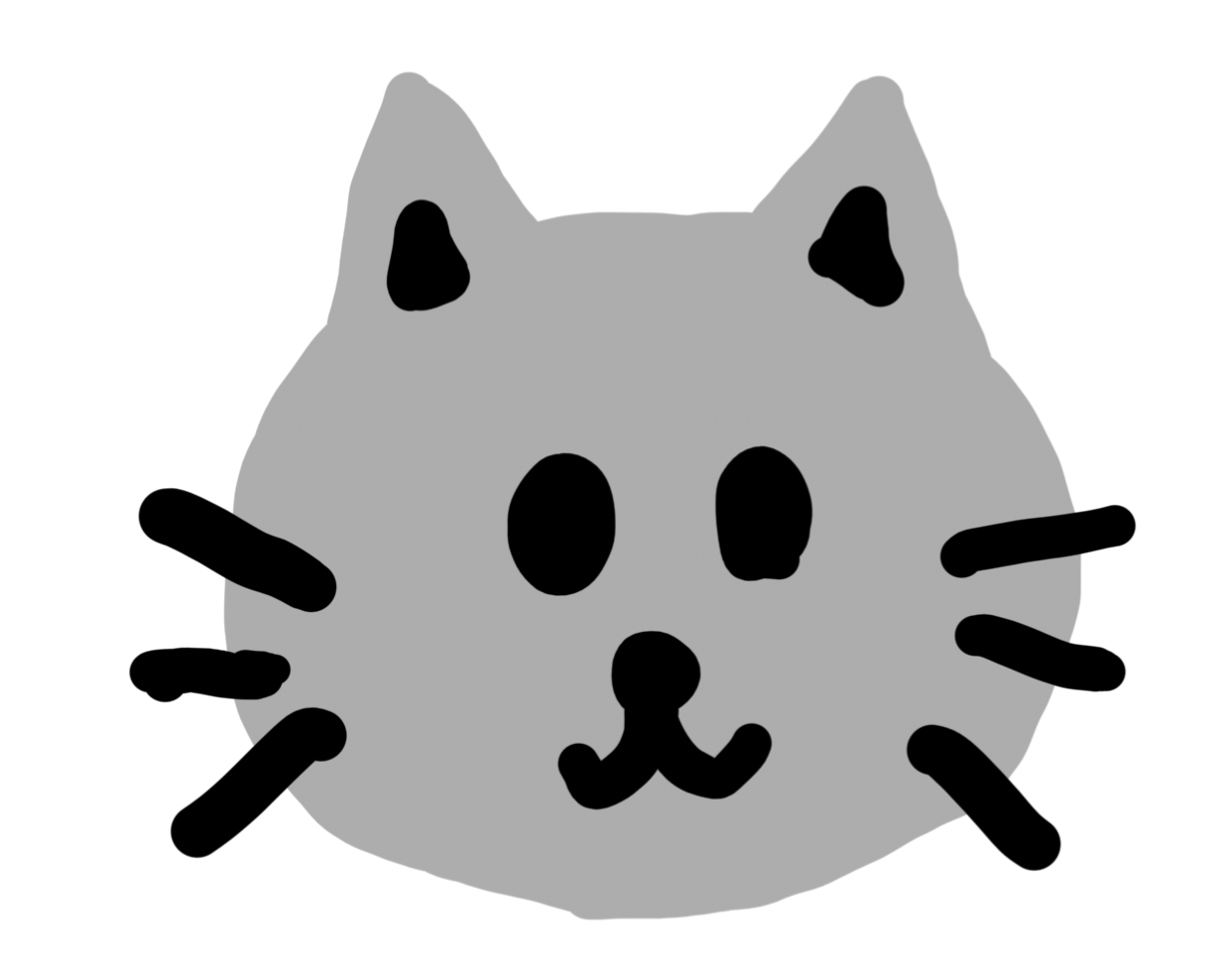
親が急に保育園に迎えに行ったり、休んだりが難しい時もあります。その時のために、祖母・祖父にたまに保育園の送り迎えをお願いしたり、短時間だけ預けたりなど子どもが元気な時に事前に練習しました。
病児保育の確保
病児保育は基本的に小児科の併設が多いです。かかりつけの小児科を探す際に、病児保育があるかどうかもポイントにしてみると良いと思います。一度受診をしていると(カルテがあると)、預けやすくなります。しかし、その日の予約枠は限りがあるので、感染症流行期などは争奪戦になります。事前の病児保育施設の下調べが大事です。
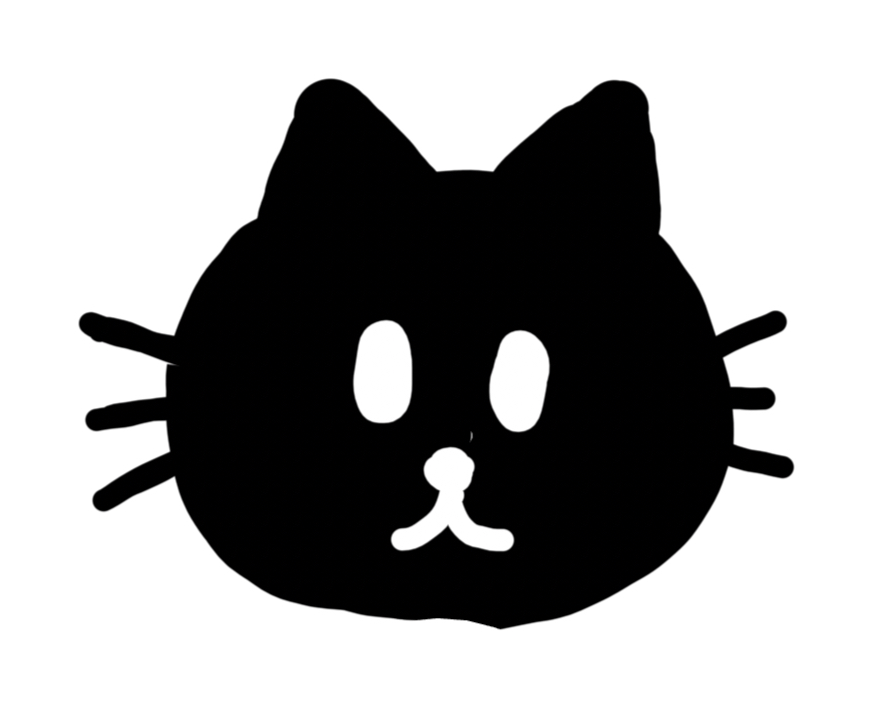
看護師や医師がしっかり見てくれるから安心。お弁当の準備とが必要だったりするので、少し準備が大変かもです。
ファミリーサポートの確保
登録制度のことが多いので、事前に登録する必要があります。
まとめ
保育園に入園するとほとんどの場合は、子どもたちは風邪をひいたりと体調を崩します。これは、免疫が発展途上な状態で集団生活をするためで誰もが起こりうることです。
事前の対策や準備でその負担感は軽減できます。家族一丸となって乗り切りましょう!!
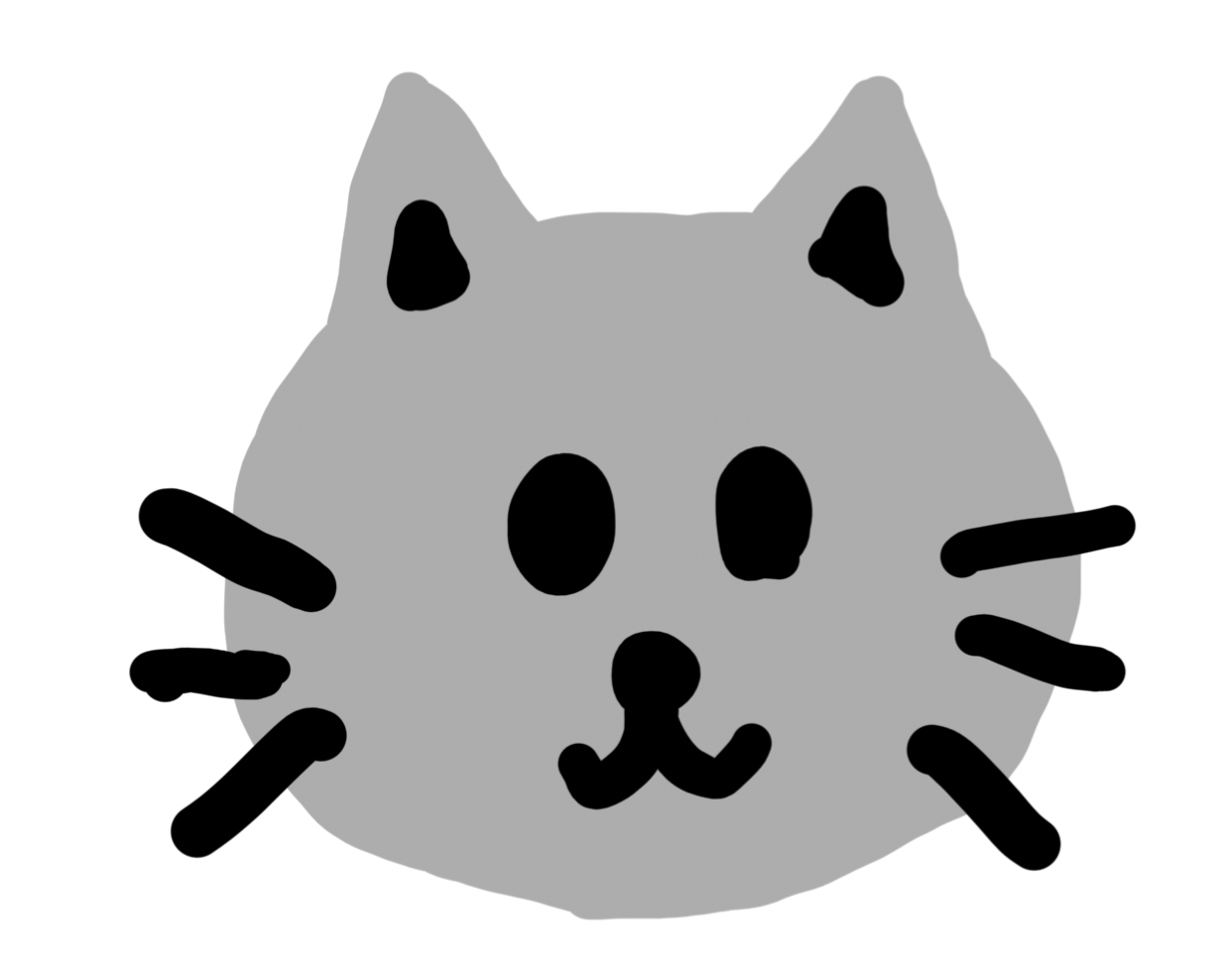
職場の先輩ママ・パパにどうやって対応していたかなどをよく聞いていました!具体的に質問できるのでとても参考になりました。みんなで乗り切りましょう!


